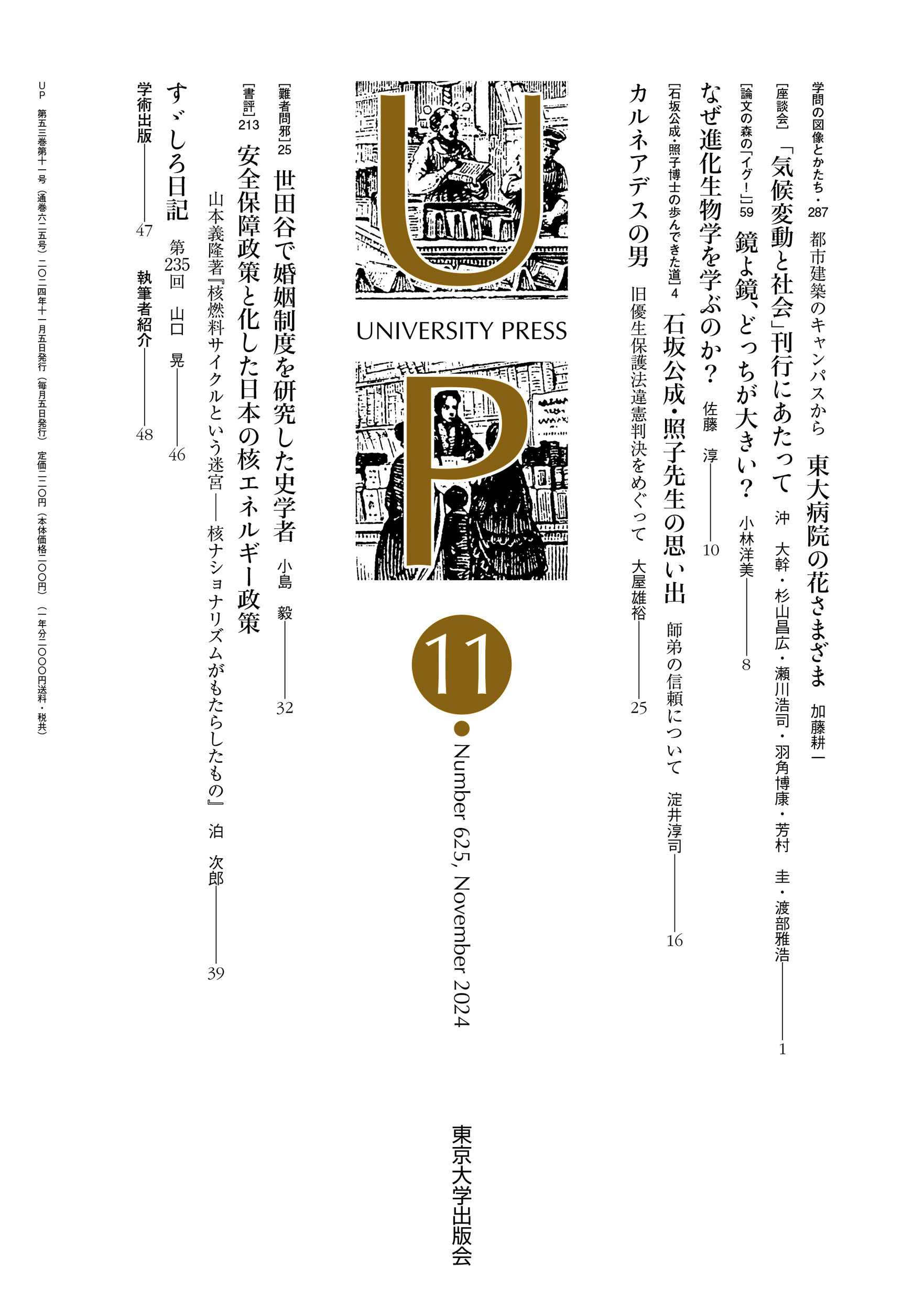東京大学出版会「気候変動と社会」刊行に伴い、編集委員が集まり、本書刊行の背景や伝えたいメッセージなどについての座談会を開催しました。
気象庁の観測によると、今年2024年7月の日本の平均気温の上昇分は+2.16℃に達した(1)(この上昇分は1991~2020年の30年平均値との差を意味する)。1898年に統計を始めてから最も高い数値となり、留まるところを知らない気温の高まりを肌身に実感させられた夏だった。ただし、地球温暖化の問題は文字通り気温上昇に耳目が注がれがちだが、生態系や人類の社会活動にも多大な影響をもたらす気候変動の問題でもあることを忘れてはならないだろう。
この7月に東京大学出版会から刊行された『気候変動と社会─基礎から学ぶ地球温暖化問題(以下、本書)』は、気候変動の問題について文理の垣根を越えたさまざまな角度から書かれた、いわば新しい入門書である。
以下に、本書の編集委員の先生方が、執筆の背景や伝えたいメッセージについて語った座談会の模様をお届けする。本書を手に取るきっかけや、理解を深める一助としてぜひ活用してほしい。司会進行役は杉山昌広先生に務めていただいた。【UP編集部】
文理統合の学びを体現する『気候変動と社会』
杉山:それではまず、編集代表である沖先生に、本書を執筆した背景について伺います。どんな思いがあって企画が動き出したのでしょうか?
沖:本書を語る上で、2022年7月に東京大学に発足した「気候と社会連携研究機構(以下、機構)」の存在は欠かせません。気候変動は社会全体の問題であり、解決には自然科学や社会科学に加え、人文学の要素が必要になります。統合された学術分野を生み出す機運の高まりを受けて、東京大学にある12の部局を横断する組織として立ち上げられたのがこの機構です(現在は13部局)。
渡部:本書を執筆したのは「機構の理念を体現する教科書を作ろう」とのアイデアがあったからです。横断型の組織を立ち上げ、問題解決につながる研究に取り組もうとしたとき、教育の基礎となる教科書は必須といえるでしょう。
沖:授業は生ものなので、その場にいる人だけにしか教えられませんし、まして時間の制約があってすべては話し切れませんからね。読んで勉強できる書物が必要になったわけです。
杉山:教科書を執筆するにあたって、どんな内容を目指したのでしょうか?
沖:「相互作用環」という用語があります。もともと京都の総合地球環境学研究所で使われていた言葉で、気候変動を含めた地球環境問題は単に物理・化学の問題、ましてや人間の業なんて話ではなく、自然と人間が相互に働きかける作用の中で生み出されるものだ、という意味です。つまり気候変動の問題解決には、自然と人間の両方にまたがる知識が必要となり、この教科書では特に「気候と社会の相互作用」について学べる教科書を目指しました。また、索引も充実させるようにみんなで心がけましたので、気候変動や地球温暖化に関する百科事典としても便利に活用していただけると思います。
瀬川:気候変動は、最も重要な社会問題と言って差し支えないでしょう。それだけに、インターネット上には正確な情報だけでなく、疑わしい情報もあふれかえっています。特に、学術的な審査を何ら経ていない不正確な話が流布されているのは問題です。誤った情報が繰り返し発信される状況にも、非常に強い危機感を抱いています。
沖:ダーウィンの進化論は嘘だと考えている人や、地球平面説を主張する人もいるように、地球温暖化への懐疑論もいまだ根強いですよね。両論併記という名目で、異論や変な論説を面白がって取り上げるメディアの責任は重大だと思います。もう数十年経つと断罪されるでしょう。
気候変動を多角的に読み解く七つの章
杉山:本書の章構成からも、学術分野の垣根を越える狙いや、誤った情報に惑わされない思考力を養う狙いがうかがえます。改めて、渡部先生から本書の構成について解説していただけますか?
渡部:本書は七つの章から構成されています。「なぜ気候変動が世界の主要課題になったのか」についてとこれまでの経緯や変遷(第1章)、システムの構成要素(第2章)や気候変動のメカニズム(第3章)、影響評価や適応策(第4章)と続きます。さらに、脱炭素技術に代表される緩和策(第5章)、ガバナンスや国際協定の話(第6章)に触れ、最後は個人レベルにクローズアップして「一人ひとりができること」を問いかけています(第7章)。
ちなみに本書は、理系向けの教科書で採用されることが多い横組み(横書き)を採用していますが、文系の学生にも読みやすいように留意しました。
瀬川:日本独特の事情かもしれませんが、高校の高学年で文系と理系に振り分けられて、それ以降は知識や思考方法に偏りが生じてしまうという問題がありますよね。気候変動の課題に立ち向かうためには、幅広い知識を多角的にバランスよく検討する学際性が求められると思います。
渡部:やはり大学においても、文系と理系は明確に線引きをされています。それだけに本書では、どちらの学生が読んでも新たな知識を得られるように心がけました。
杉山:本書は平易な内容を心がけつつも、情報の密度や深さがありますよね。類書との比較でいえば、この分野の入門書として有名なアンドリュー・E・デスラーの『現代気候変動入門』(名古屋大学出版会、2023年)では、アメリカの社会を念頭に書かれていますが、本書では世界と日本を対比しながら書かれている点が大きな違いだと思います。
編集委員が語る各章のハイライトとは?
杉山:続いて、各章の注目すべきポイントや強調したいことを順番に伺います。まず沖先生、第1章は歴史的な観点も含めて非常に広範な内容でしたね。
沖:「気候変動への対策を講じるのは当たり前」と大上段から押し付けるのではなく、「気候変動にはどんな問題があって、なぜこれほどの社会問題になっているのか」を理解してほしい、との思いがこの章の背景にはあります。人口やGDP、エネルギー消費や森林面積の変化なども含め、今までの経緯と今何が起こっているのか、そしてこれから何が起こり得るのかを俯瞰的に理解できる基盤の提示が大切だと考えました。
いまだに「世界の人口は指数関数的に増え、人類はいつか破綻する」と考えている人が少なくない現状ですが、実際は今世紀のどこかでピークを迎えそうです。だとすれば、今世紀をなんとか乗り越えれば、持続可能な社会を実現できるはず。そんな希望も伝えたかったのです。
杉山:悲壮感を漂わせながら対策に頭を悩ますだけでなく、「希望はある」と伝えることも本書の大切なメッセージですよね。続く第2章について、羽角先生いかがでしょうか?
羽角:第2章では、後の章でも言及されるシステムの定義を解説しています。特に重視したのは、共著者たちが有する専門知識に一貫性を持たせることでした。本章でシステムの定義を「気候・生態・社会」に分けたのは、機構の三つの部門(地球システム変動研究部門、生態システム影響研究部門、人間システム応答研究部門)との関連を意識しているからです。
これらのシステムを改めて定義し、文章で説明する経験はこれまでなかったので、正直なところ苦労しました。記された内容をストーリーとして読み取り、個々のシステムの繋がりを見出してもらいたいですね。共同で執筆にあたった杉山先生はいかがですか?
杉山:特にこの章では、機構の特色を表せたと思います。全体像を整理して捉えつつ、「だからこそ、多様な学術分野が必要になる」と綺麗にまとめられたのではないでしょうか。それでは続いて、第3章の解説を渡部先生からお願いします。
渡部:第3章は、私を含めて六人で執筆しました。将来的な気候の変化、過去の気候の変化、気候変動予測のベースになるシミュレーションなどについて解説しています。この章だけ切り取れば類似の解説書は存在しますが、これらの内容が本書に盛り込まれていることに大きな意味があると思います。気候変動の問題に触れると、「そもそも将来の気候予測はどのように行われているのか?」との疑問が当然挙がるはずですから。
ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎さんが提唱した頃から約50年の歳月をかけて積みあげた気候科学の考え方を説明した上で、将来の気候がどう変化するか、そもそもどう計算されているのか、どれぐらい信用できるのか、といった論点を盛り込んでいます。
沖:この章では、なるべく数式を使わずに気候変動の原理を説明していますよね。とてもご苦労されたのではと想像しますが、いかがでしょう?
渡部:おそらくこの章の内容は、数式で説明すれば理系の学生は明快に理解できると思います。しかし、「式なんか見たくもない」と感じる人でも正しく理解できることが、本書における私たちの目標です。「式を出せばそれで済む」との考え方は、やや言いすぎかもしれませんが、理系側の人間の驕りではないでしょうか。
杉山:章の最後に一つの数式は登場しますが、確かに極力省かれていますよね。渡部先生の姿勢は、文章からも読み取れると思います。では第4章について、芳村先生からお願いします。
芳村:第4章では、影響評価について解説しました。生態系や人間社会を中心に、気候変動が及ぼす影響と考えられる適応策を中心に述べており、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第二作業部会のレポートに対応する内容です。私を含めた七人の著者が執筆し、機構の生態システム影響部門からも加わってもらいました。
影響評価は、実に多様な分野の研究者が取り組んでいます。それだけに各分野に隔たりがあって、たとえば一見すると関連が深そうな陸の生態と農業の間には、ほとんど繋がりがないと言えるほどです。これまで皆さんが語ったように、「影響評価の分野でも、もっと繋がりを強めよう」と意識し、章の構成にも反映しました。
ただ、すべての領域を網羅するのは大変難しいのも事実です。この章では、IPCCのレポートで八つの章に分けて論じていることを、「自然災害・陸上生態・海洋生態・健康・都市」という五つのサブセクションに再構成しました。
杉山:IPCCの部会でも、地域ごとに章が分かれているように、部門ごとの違いだけでなく地域ごとの違いがある、言ってみれば不均一な特色がある分野ですよね。
芳村:本章のコラム4・1では「影響評価モデル群」を取り上げ、従来独立していたセクターと、それらの統合について述べています。おっしゃるように、現状の不均一さも含めて伝えようと考え、あえてこのコラムを執筆しました。
長く支持される入門書を目指して
杉山:では、第5章については私から。気候変動の課題や対策を日本と海外で比べると、共通点もあれば、異なる点もあります。たとえば瀬川先生の専門でもある太陽光発電に言及すると、グローバルでは最も安価な再生可能エネルギーになりましたが、日本ではコスト面の課題が残っています。
ほかにも、反すう動物のゲップで発生するメタンの量や、森林破壊の規模など、国によって事情はさまざまです。この章では、国や地域による事情に加え、世界の潮流も踏まえつつ、日本における緩和策を解説しました。
瀬川:政策的な判断を行うには、当然ながら最新の情報が必要になります。しかし実際には、研究者でさえも少し専門分野が離れただけで最新の情報を手に入れにくいし、ましてや研究者以外の人たちはなかなか知ることができません。そこで第5章では、なるべく最新の情報を盛り込むことにこだわりました。ただ情報はアップデートされていきますから、この本のすべての内容が将来にわたって最新だと言えるわけではないのが歯がゆい点です。
渡部:これから先も知見が積み重なって、情報はアップデートされていきます。改訂の機会を得られれば、その時点で最新の知見を入れ込むこともできるでしょう。本書が末永く支持される教科書になれればいいですよね。
沖:一方で、長い時間が経ったのちに本書が読まれると、「当時の緩和策はこんなふうに考えられていたのか」や「社会にはこんな軋轢があったのか」といった部分は、文章からにじみ出て残っているでしょう。その意味では、過去を振り返る資料となる価値も十分に期待できると思います。
杉山:次の第6章では政策について解説しました。緩和策と同様にダイナミックに変わり続けている領域ですが、この章でもなるべく最新の情報を盛り込みつつ、「なぜこうなるのか」を考えられる構成になっています。国内政策や国際的な枠組み、持続可能な開発などに言及しましたが、各論だけにとらわれず、「民主主義の原則に立った場合、気候変動の問題をどう考えればいいのか」との根本的な問題について語ったのがこの章の内容です。
答えの見えない問いを考え続ける重要性
杉山:最後の第7章は「わたしたちに何ができるか?」について語られています。個人レベルでできることを考えると、省エネなど我慢を伴う行動を考えがちです。ですが第7章では、起業やNPO活動という手段もあるし、研究活動や勉強も大切だと伝えています。
これまでの内容を踏まえつつ、次のアクションにまで踏み込んでメッセージを発信している点は、本書の特色だと言えるでしょう。そこで最後に、皆さんから本書を通じて伝えたいことを教えていただけますか?
瀬川:理路整然とした根拠や客観的な資料にもとづく思考が肌感覚に染み付いている学生もいれば、そのような思考に不慣れで、権威ある人が言ったことを鵜呑みにしてしまう学生もいます。学生さんには、本書を通じて、きちんとしたエビデンスに基づいて客観的に判断できる軸を持ってほしいですね。
羽角:仮に私たちが本書を通読しても、すべて理解するのは骨が折れます。初学者やバックグラウンドがない人たちはなおさらでしょう。それでも、やはり拾い読みはしてほしくありません。各章や各項目の繋がりを見出してほしいと思います。
渡部:本書の内容すべてに精通している研究者はほぼいないでしょう。つまり本書を深く理解することは、誰もできないことを成し遂げる足掛かりになるかもしれません。もちろん本書を読めば完璧とまでは言えませんが、最初のステップとして役立つことを期待しています。
芳村:第7章で「何をすべきか」まで踏み込んだ内容は、私たち全員のコンセンサスでもあります。本書を読むことは、自分が納得して行動できるベースを得られる。そう信じて読み進めてほしいです。
沖:「できることから始めよう」で留まってしまうと、そこから先には広がりません。すぐには答えがみつからない疑問や課題、オープンエンドなクエスチョンと向き合う訓練も、私たちには必要ではないでしょうか。本書を通じて、立ち止まらずに考え続ける大切さも感じ取ってもらえたらうれしいですね。
(1)https://www.jma.go.jp/jma/press/2408/01a/20240801_julytemp.html
(2024年8月13日、オンラインにて収録)
(構成協力:和田翔)
※本記事は、東京大学出版会UP 2024年11月号に掲載されたもので、東京大学出版会より許可を頂き再掲したものです。