学術フロンティア講義「気候と社会」第9回目の講義は、気候変動に関する国際交渉を研究対象とされてきた亀山康子教授(本学新領域創成科学研究科)をお招きし、「気候変動対処のための国際制度」をテーマとして、これまでの気候変動に対する国際的な取り組み状況を分かりやすく解説いただきました。
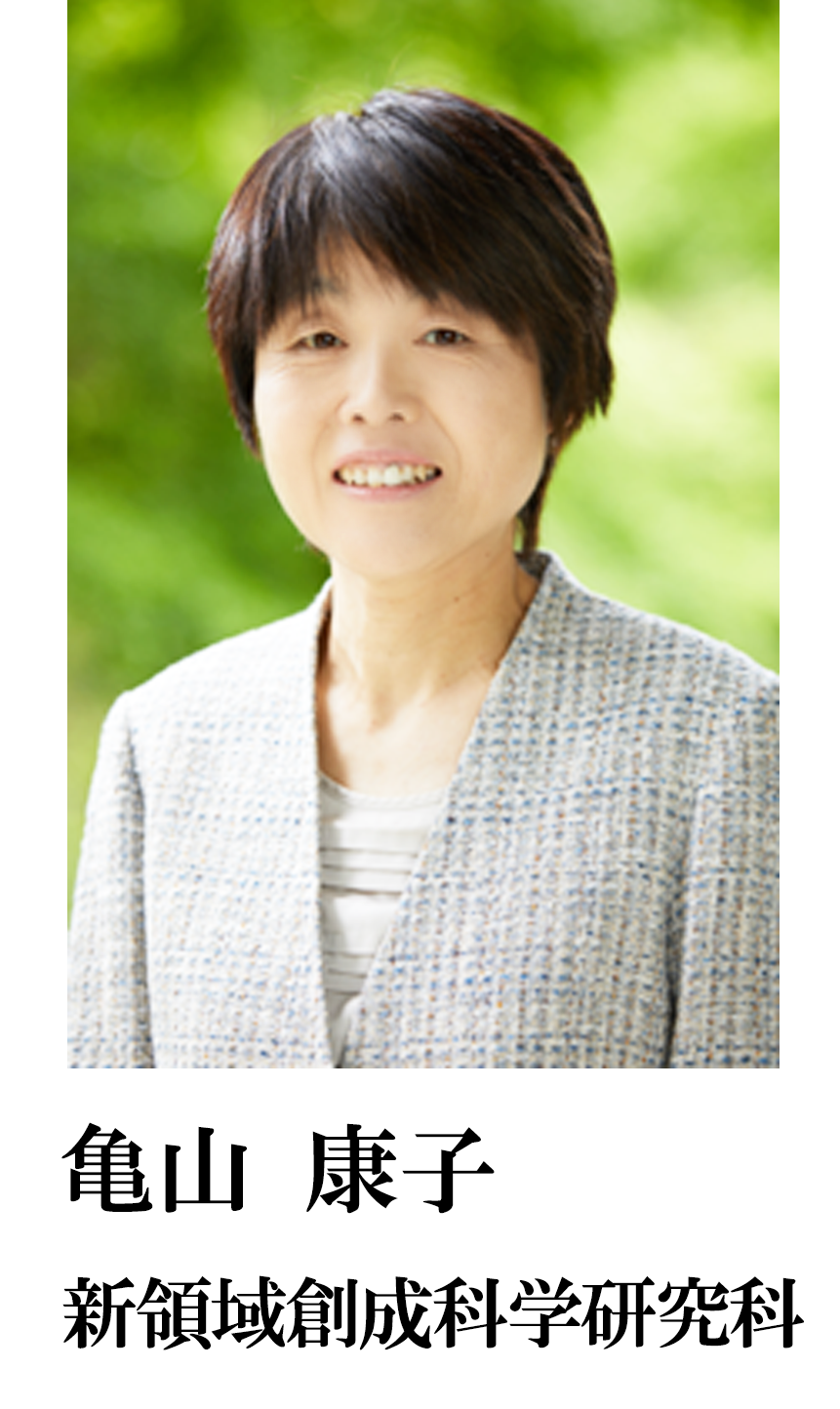
講義の主な論点は以下の通りです。
- 気候変動への3つの対応:緩和策、適応策、損失・損害
- 気候変動交渉の歴史:気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定、COP21以降の動き
- 20世紀型と21世紀型の地球環境条約交渉の構造
- 気候変動への対応を変える要因:Cost of action と Cost of inaction
- 米国、欧州、英国、日本の温室効果ガス(CO2)排出削減の動向
- 緩和策の類型:規制的手法、経済的手法、情報的手法
亀山先生は、まず、気候変動への対応として緩和策、適応策、損失・損害があることを挙げ、エネルギー利用など「Drivers (D)」、温室効果ガス排出量増加など「Pressures (P)」、気温上昇など「State (S)」、異常気象による損失損害など「Impact (I)」、排出量削減のための政策導入など「Responses ®」で構成されるダイヤグラムを用い、現象と研究の位置づけを説明されました。その中で、気候変動が起きるだろうということは30年前から指摘されていたが、D-P-S-I-R間の因果関係を確実に立証するのに時間がかかり、社会の対応が遅れたと示唆されました。これまでの授業の内容も復習しつつ、温室効果ガス排出量増加について、日本ではCO2がメインだが世界では他のものも多いこと、京都議定書採択以降の中国などの増加が著しいことを示されました。20世紀型国際交渉は、各国政府間の合意内容を持ち帰って実施する構造だったのが、21世紀はインターネット等の普及により、様々なセクターが直接対話できる状況に変わったことが、パリ協定の構造に影響しています。パリ協定採択の頃には、国が決めなくても自治体、企業、市民等が自発的に取り組むようになりました。過去にはCost of actionが重く感じられ、国際社会で義務を課す必要があったのに対し、近年では気候変動の被害が現れ、対策をとることが合理的判断という状況となったためです。米国ではシェール革命で石炭から天然ガスへの転換が進んだり、再生可能エネルギーが安くなって導入が進んだりなど、意識が高くなくても排出削減が進んだこと、欧州は意識高く削減を進めていること、英国では1860年代並みまで排出削減が進んでいること、などが示されました。その上で、数%削減と異なり、排出量を最終的にゼロにするには、社会そのものを大きく変えなければならないことを強調されました。最後に、レポート課題と関連し、海外メディアの情報から気候変動の影響の大きさを感じてほしいと締め括られました。
<まとめ:中崎城太郎>



